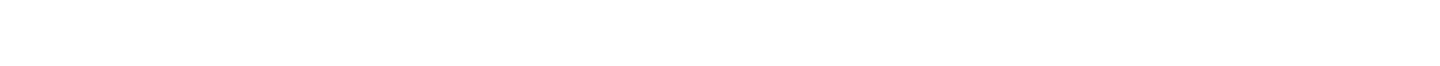今年の記録的な空梅雨で各地が厳しい暑さに見舞われていますが、先日私たちは再び能登輪島を訪れました。
思い返せば前回の10月は、能登が前代未聞の豪雨に見舞われた直後でした。街の至るところで深刻な被害の痕跡が見られ、活動内容も、地震で被害を受けた家財の搬出に加え、山から民家へ流れ込んだ土砂をひたすら掻き出し運び出すというものでした。重なる自然災害に現地の方々の落胆が隠せない様子を今でもはっきりと覚えています。数日間という限られた時間でしたが、能登の現状を肌で感じ、忘れがたい経験となりました。
そして今回も、これまで多くのご縁のあった輪島市で活動してきました。もちろん車にはたっぷりのビールを積んで。

なぜビールを?
発災以降、私たちはこれまでに延べ15,000本以上のビールを能登に届けてきました。それは、私たちが「美味しいビールを造ることにとどまらない」という考えを大切にしているからです。ビールを通じて、飲む人も飲まない人も含めて、社会やコミュニティに良い影響を与えたい。そんな想いのもと、被災地では「ほっと一息ついてもらいたい」という願いを込め、昨年の4月「望み」という名前のビールを造ってメッセージと共に届けたのが始まりでした。以降も、その時々の限定ビールを直接届けたり、人の手を借りて現地の方々へお渡ししてきました。今回も、小さな自家用車に積めるだけのビールを詰め込み、早朝の京都を出発しました。

輪島に着いて感じたこと
琵琶湖の西を北上する道中、前方の視界をほとんど奪われるほどの大雨に遭遇しました。ところが日本海側に出ると、一転して青空が広がり、美しい海岸線を横目に軽快に能登へと車を走らせました。
途中、工事中の道路やうねる迂回路もありましたが、昨年に比べると補修が格段に進んでおり、走行に不安を感じることはありませんでした。複数の箇所の工事が順次というより同時に進んでいる光景に、暑い中で作業する方々への感謝と、復旧にかける地域全体の力強さを感じながらハンドルを握りました。
午前10時頃に輪島へ到着し、前回もお世話になった石川県ボランティア協会の下さんと合流。その後、10か月ぶりに輪島市内を見て回りました。損傷したままの建物は減り、解体が大きく進んだ印象です。象徴的だった横倒しの7階建てビルも姿を消し、昨年10月ごろに公費で解体されたとのこと。仮設住宅も整備され、多くの方がそこで生活しているそうです。
ただ、解体後に家を再建するかどうか、大きな決断に迫られている被災者も多く、特に高齢の方にとっては厳しい選択です。仮に建てるとしても建設業者や資材が不足しており、完成まで数年待つ場合もあると聞きました。仮設住宅は原則2年間の入居期限がありますが、石川県は延長を働きかけており、条件付きで1年間の延長が認められる予定とのこと。それを聞いて少し安堵したものの、生活の基盤である「住まい」が依然として大きな課題であると実感しました。
下さんとの再会を喜ぶ間もなく、すぐに下さんの車に乗り込み、京都醸造のビールを持って地域の方々を訪問しました。漁業関係者や森林関係者、災害ごみの回収をされている方、大きな木材工房など、さまざまな現場へお邪魔しました。突然のささやかな差し入れにもかかわらず、どこでもとても喜んでいただき、「じゃあ今日は昼で仕事を切り上げて一杯やりますか!」といった冗談まで飛び出し、こちらも嬉しい気持ちになりました。中には「去年『望み』というビールをもらいましたよ」と覚えていてくださった方もいて、輪島が本当に大変だった時期を思い出しつつも、胸が熱くなるような時間になりました。


どのような活動をしてきたか
ビールを各方面にお渡しした後は、下さんと一緒にトラックへ乗り替え、解体や改修工事で出る廃材を臨時の集積場に運ぶ作業を手伝いました。前回は湾岸エリアに集積場がありましたが、現在は「健康の森」というキャンプ場施設の中に、より大規模な集積場が設けられていました。廃材は種類ごとに細かく仕分けられ、次々と入ってくるダンプを効率よくさばく様子は非常にシステマチックで印象的でした。


二日目は、まず輪島市たすけあいセンターのテントでボランティア登録を行い、その後、活動ごとにグループ分けされました。私は8人編成のグループの一員として、少し離れた地域にある民家の蔵から依頼者さんの父や祖父の遺品を救出するミッションにあたりました。
稲が青々と茂る自然豊かな地域にその家はあり、横には立派な蔵が建っていました。地震で土壁が崩れ、入口が閉ざされていたため、まるでアクション映画さながらに厚さ10センチはある扉をこじ開け、汗とほこりにまみれながらバケツリレーで中の物を運び出しました。中には、戦時中に亡くなられた祖父が家族に宛てた手紙や装飾品もあり、一緒に汗だくになった依頼者さんの表情には安堵が浮かんでいました。また、グループ内にも達成感と心地よい連帯感が広がったのを感じました。


勢いづいた私たち8人は、本部テントに戻ると、もう一件別の活動に向かいました。地域の神社で出た落ち葉や木材ごみを、先ほどの集積場に運ぶ作業です。数台の軽トラックに分乗し、30分ほどで手際よく積み込みを終え、きれいになった境内を後にしました。
私が運転するトラックに同乗したのは、長野県から来た歯科医の男性でした。能登各地でのボランティア活動の話や印象に残った出来事を楽しそうに語ってくれ、その姿勢にこちらも気持ちが高まり、車内はとても賑やかになりました。彼は歯科医として、活動の合間に被災者の口腔ケアの相談にも応じているそうで、他者を思いやる行動に深く感心しました。(後日、先生が執筆した能登に関する丁寧なレポートや新聞記事の切り抜きを京都まで送ってくださいました。)

三日目は、輪島の復興支援団体「リガーレ」の皆さん、明治学院大学の学生さんたちと共に、輪島漆器用の木材を損傷の酷い倉庫から救出する活動に取り組みました。建物の中では膨大な数の板がジェンガのように不安定に積み上がっており、慎重に一枚ずつバケツリレーで搬出しました。作業を進めるうちに倉庫に光が差し込み、見違えるようにきれいになっていきました。
一緒に活動した学生たちの明るい声とパワーは現場を活気づけ、厳しい暑さの中でも作業を苦に感じさせない不思議な力がありました。昼休憩には、そのちょっとした時間を利用して近くの神社で彼らが持参したドリップコーヒーを街の人々に振る舞う企画の準備もしていたりと、若い彼らの前向きで素晴らしい取り組みに感心しました。


話は戻りますが、このとき倉庫から運び出した木材は、輪島塗漆器の素材となるものです。素人目にも、どの板も木目が美しく、触れると上質な木であることがはっきりとわかりました。
今回、初日に訪れた四十沢木材工芸さんも、こうした厳選された無垢材を加工し、お皿やトレーなどの素敵な製品を数多く手がけています。木目の端正な美しさと、丹念に磨き上げられた手触りには、思わずため息が出るような心地よさがあります。
しかし昨年の地震発災時には、大きな木材倉庫に積まれていた材料が崩れ落ち、工場と加工用の機械も大きな被害を受け、しばらく製作ができない状態が続いたそうです。全国各地からの応援により工場の仮復旧ができ、今では製作も半分ほど再開されています。


輪島の魅力のひとつであるものづくりが、このように荒波を乗り越えて継続されていることは、地域の人々にとって何よりの希望につながっていると感じました。洗練された製品が並ぶ素敵なギャラリーも併設されていますので、輪島を訪れた際にはぜひ立ち寄ってみてください。工房で働く方々にも京都醸造のビールを差し入れし、喜んでいただきました。
現地団体の紹介(復興支援団体「リガーレ」)
三日目の活動でお世話になった復興支援団体「リガーレ」について紹介します。
輪島市の公式ボランティア活動は現在、受け入れ枠が縮小傾向にあり、金・土の週2日のみオンラインで事前申し込みが必要です。しかし各日には上限人数があり、すぐに枠が埋まってしまうため、参加を諦めざるを得ない人も少なくありません。
さらに、5月末で市民からの作業依頼(ニーズ)の受付も終了したそうです。さまざまな事情があるとはいえ、この流れは今後も続きそうです。
そんな中、行政のボランティアセンターでは拾いきれないニーズ――「誰に頼めばいいかわからない」「遠慮して声を上げられない」といった市民の声――に応えるため、昨年10月に新たな団体が立ち上がりました。それが復興支援団体「リガーレ」です。


「リガーレ」とはラテン語で「結ぶ」を意味し、人と地域、人と人を結びつけるという理念のもと、輪島の復興や市民の生活再建に深く寄り添った活動を続けています。特に印象的だったのは、メンバーが現場対応力を高めるために技術を学び、一人ひとりができることを増やそうとしている点です。例えば、損傷した屋根にブルーシートをかけるだけでも知識とコツが必要ですが、彼らはそうしたスキルを積極的に習得し、行動しています。
被災地の市民自身が組織した団体だからこそ、「外部の支援を待つのではなく、自分たちの街は自分たちで守る」という強い決意を感じました。
詳しい活動内容や支援方法は、ぜひ以下のリンクからご覧ください。活動資金の寄付も受け付けていますので、可能であればサポートをお願いします。
復興支援団体「リガーレ」のHPへ
活動を終えて感じたこと
数日の活動を終え、そこで出会った一人ひとりの顔や言葉を思い出しながら、輪島を後にしました。地元の人々からは、輪島という土地への深い愛情が言葉や仕草の端々に感じられ、この街の復興を心から願う気持ちに改めてさせられました。また、自らも仮設住宅で暮らしながら、日中はほぼ毎日ボランティア活動を続けている方とも一緒になり、いたたまれない気持ちと同時に、被災地で生きる助け合いの精神の素晴らしさに強く心を打たれました。
離れて暮らしていると、メディアを通して輪島や能登の話題を見る機会は減っていきます。しかし実際に足を運び、街を歩き、人と話すことで、震災からまもなく2年を迎える今もなお、傷跡は完全には癒えていないことを痛感しました。同時に、誰かのために黙々と動き続ける人々――勝手に「黙々人(もくもくじん)」と呼んでいますが――の存在をまた身近に感じました。 困難な状況の中でも前を向いて進む人々の強さに触れ、多くの刺激をもらいました。
あと、方々で聞かれたのは、王道であるボランティアセンターでの登録以外にも活動の拠点はあるということ。現地の社会福祉協議会や先述のリガーレ、その他独自に活動されている団体(災害NGO結さんなど)に直接問い合わせをしてみるのもいいと思います。もしくは現地での当日登録枠もあるので、朝にセンターへ行ってみるというのも可能性があると思います。

また、滞在型のボランティアのボトルネックは、「宿泊」です。まだ営業している宿泊施設が限られているため、空室が見当たらない、もしくは室料が異常に高騰してるケースが多い。なので車中泊されてる方や片道45分ほどの市外で宿を確保している方もいらっしゃいました。気候がもう少し穏やかになればキャンプ場でテントを張って活動をするのもいい選択肢になるかもしれません。これについても直接、先述の団体に相談してみるのがいいと思います。
「今の能登、これからの能登に自分は何ができるのか」という問いを胸に、今回も輪島を後にしました。また訪れたいと思います。

■ 災害ボランティア車両の高速道路の無料措置について
・Nexco 西日本: https://corp.w-nexco.co.jp/newly/r1/0830/
・Nexco 東日本: https://www.e-nexco.co.jp/news/important_info/2019/1018/00002623.html
■寄付金および支援金の受け入れ先
・復興支援団体「リガーレ」 https://wajimaligare.net/
・石川県災害義援金: https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suitou/gienkinr0609.html
・日本赤十字社:https://www.jrc.or.jp/chapter/ishikawa/about/topics/2024/0925_042897.html