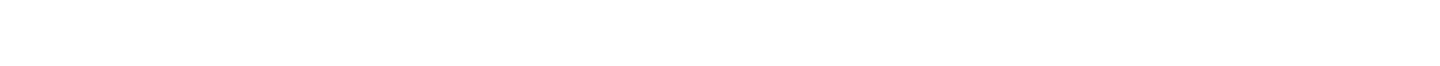【無濾過非殺菌とは?】
ビールや日本酒のうたい文句に「無ろ過非殺菌」というのをよく目にするかと思います。これは読んで字の如く、ろ過する工程を経ていないこと、そして火入れなどの滅菌工程を経ないことで菌類、特に酵母菌が生きたまま残っているということを意味します。
日本酒でいうと"しぼりたて"に近い、米の甘味やフレッシュな香りが感じられ、味わいも濃くしっかりと残っているという特徴がある"にごり生酒"がそれにあたります。ビールでも、麦芽の旨味やホップの繊細なアロマやフレーバー、そして酵母由来のフルーティーで活き活きとした味わいが、この「無ろ化非殺菌」という製造方法によって叶えられるです。では、このろ過(濾過)という工程は、ビールにとって、そんなに悪いものなのでしょうか。ろ過をすることによるメリットとデメリット、そして、それに代わる現代的な製造方法「遠心分離」について今日は少し掘り下げてみたいと思います。

クラフトビール業界の多くの醸造家にとって、「ろ過」に対しては、少し複雑な想いをもっていることがあります。それは、ビールにできるだけ多くの香りや味わいをそのまま残したいと考える醸造家の中には、「ろ過はそれらを奪ってしまう敵だ」と考える人がいるからです。実際、それは半分正解です。
【濁り=個性としてとらえる時代の到来】
クラフトビール黎明期には、ほとんどのビアスタイル(IPAも含めて)において、ろ過はほぼ必須の工程でした。当時の考え方としては、ビールの濁りは欠陥とされることが多く、実際にそうである場合も少なくありませんでした。ですが、時代を経るにつれ、ホップの使用量も増え、IPAのレシピが進化し、消費者の好みが変わっていく中で、濁りはむしろユニークな特徴として歓迎されるようになりました。

しかし、従来のろ過方法をそのまま現代的なスタイルに適用したところ、多くの醸造家が「ろ過後のビールから本来あるべき、期待していた風味までもが失われている」と感じるようになりました。その理由は、当時一般的だったろ過媒体(珪藻土、フィルターパッド、レンズフィルターなど)が、非常に微細な粒子まで除去してしまう仕組みだったからです。つまり高度に発展したフィルタリング技術でビールは見事にクリアになる一方で、ビールの魅力でもあるホップオイルや風味成分も一緒に取り除かれてしまっていたのです。
特にIPAの場合、ホップの使用量が増えると、アロマや味わいの素であるビール中のホップオイル量も増えます。このホップオイルは濁りの原因となるだけでなく、酵母やタンパク質、ホップ由来の微粒子などに結びつく性質があります。つまり、ろ過の過程でそれらの固形物を除去すると、同時にホップオイルや風味成分まで取り除いてしまうわけです。
このため、「ろ過はビールをだめにする」と考える醸造家がいるのも無理はありません。しかし、それがすべてではありません。
実際、この「取り除く」工程は、ラガーやピルスナー、ケルシュなど、クリーンでキレのある味わいを求めるビールにおいてはむしろプラスに働きます。さらに、ビール内の有機物を除去することはビールの保存性にとって非常に重要で、残留した有機物は時間の経過とともに分解し、劣化臭や不快な味わいを生じさせる原因になります。ビールに含まれる有機物の量や種類はスタイルごとに異なり、それが賞味期限や保存安定性を左右する大きな要因のひとつでもあります。
では、ろ過せずに「不要な有機物を取り除きながら、香りや風味成分は残す」にはどうすればいいのか。ここで登場するのが遠心分離機(Centrifuge)です!

【醸造家の理想を叶える夢の装置”遠心分離機”】
遠心分離機自体は昔から大手ビールメーカーで使用されている装置で、最終ろ過の前にビールを予備的に清澄化する目的で使われていました。仕組みとしては、円錐型のディスクを容器内で高速回転させ、比重の重い固形物を外側に飛ばすことで液体と分離させるというもの。
現代の醸造家たちは、この遠心分離の度合いをうまく調整することで、どの程度の固形物をビールから取り除くかを細かくコントロールできるようになりました。つまり、同じ装置でありながら、ピカピカに透き通ったラガーから、濁りを残したヘイジーIPA、さらには酵母をそのまま生かしたヘーフェヴァイツェンまで処理できるのです。

この遠心分離機は、成長するブルワリーにとって最も重要な投資のひとつと言っても過言ではありません。タンクの底にたまったホップや酵母の残留物を効率よく処理することで、製造中に発生するロスも軽減するだけでなく、有機物を減らすことで、ビールの保存安定性が高まり、長期間にわたり品質を維持することができるようになります。そしてもちろん、ろ過ではなかなか叶わなかったビールの魅力である香りや味わいを最大限に保ったままこれらのことができるのです。
京都醸造では昨年、この遠心分離機を導入しました。KBC2.0という新しい取り組みの中で、ホップを前面に押し出したビールをたくさん造り始めたタイミングとほぼ同じです。この遠心分離機を使うことにより、多種多様なスタイルのビールの状態をより正確にコントロールできるようになり、狙った味わいを長く維持できるようになりました。

すこし余談ですが、私(ジェームズ)自身、アメリカのクラフトビール業界で遠心分離機の導入が始まった初期の現場に立ち会う機会がありました。当時は、遠心分離機でわざわざ濁ったビールを造るなんて、遠心分離機のメーカー側でも想定外のこと。メーカーの担当者からはよく「そんな使い方をしたらビールが濁ってしまいますよ」と言われましたが、私は「それが狙いなんです!」と答えたものです。すると、決まって少し困惑したような表情を返されました(笑)。
その後、メーカー側もホップがたくさん入った現代的なビールに対応できるように改良を重ね、今ではクラフトブルワリー向けの遠心分離機で「ヘイジーIPA対応モデル」まで登場しているような状況です。