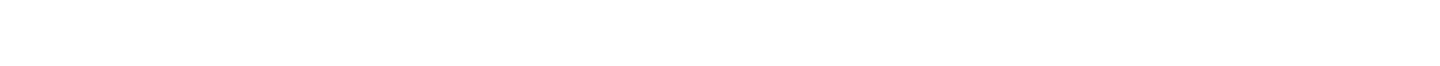今年の1月、「定番商品のアップデート」(京都醸造の今を体現する - 定番商品のアップデート)と題した記事を公開し、定番3種それぞれのラベルデザインの刷新だけでなく、レシピも大きく見直し、今の京都醸造を反映するような理想的な定番へとアップデートをおこなったことをお伝えしました。

その中でも特に大きな変更となったのが、定番中の定番であるセゾン「一期一会」の缶内二次発酵製法への転換です。そして、この度、この「一期一会」を要冷蔵から冷暗所保管可能製品へと変更することを決めました。クラフトビールにおいて、要冷蔵ではない製品というのは、大変画期的なことです。今日は、一期一会の保管方法を大胆に変更した背景についてお話したいと思います。
本題に入る前に、定番であるが故になかなかあらためて取り上げることも少ない一期一会について、まず少し紹介したいと思います。
【最初に定番化した京都醸造のセゾン】
私たちを最初に醸造所を立ち上げてまで造りたいと思わせ、そして一度限りではなく年間を通して味わいたい、提供したいと考えるきっかけになったビールが「セゾン」でした。軽やかなボディに、キリッとドライで爽快な飲み口。いわゆる国内で「ビール」と呼ばれるスタンダードなビールよりも、ずっと豊かな個性を持ち、一日中でも飲み続けられる――そんなセゾンの魅力に惹きつけられ、これだ!と感じたのを今でも覚えています。当時、国内の多くのビアバーや酒屋さんでこのビールを見かけることはほとんどありませんでした。
そして創業以来、ベルギーの伝統的なビールスタイルとモダンなアメリカのホップを掛け合わせた製品を多く造ってきた私たちですが、中でも京都醸造のビール造りの想いを体現する定番ビールとして造り続けてきたのが、この「一期一会」です。

一期一会の魅力は、その「バランスの良い味わい」と「食事との合わせやすさ」にあります。決して特別にホップが効いていたり、副原料が主張するタイプではなく、ベルジャン酵母由来のスパイシーで果実味を感じさせる味わいが魅力であり、モルトもやや控えめに滋味深さを演出しています。この酵母から引き出されたフルーティーなエステル香がホップの柑橘やハーブに近いフレーバーと溶け合い、それがどちらの香りか区別がつかないほど自然な調和を生み出しています。

もうひとつのベルジャン酵母の特長であるドライな仕上がりが、すっきりと爽快な飲み口を一期一会に兼ね備えていて、そのことから、様々なタイプの料理と合わせやすく設計されています。例えば、地中海料理のような魚介を使った料理や鶏肉料理はもちろん、ハーブやスパイスが効いた料理やフライなどにもよく合います。
【一期一会をより本格的に】
京都醸造の定番として長らく幅広い支持を得てきたこの一期一会を、より本格的なものにできる要素を挙げるとすれば、本場ベルギーのセゾンのように容器の中で再発酵を行い、その過程で自然な炭酸を得る缶内二次発酵を施すことだと考えており、この1月の定番アップデートを機に思い切って踏み出しました。
伝統的なベルジャンスタイルに日本の材料でひねりを加える帰還シリーズや、京都限定の山椒を使ったウィット「はばかりさん」などでも採用するこの二次発酵製法については、これまで度々取り上げてきました。なぜこの製法に私たちが大きな魅力と希望を感じているかについて、ここで改めてお話しさせてください

現代のビール造りにおいて一般的な、製造工程で炭酸ガスを注入しシュワシュワとした泡を添加する強制発泡に対して、一次発酵が終了したビールに酵母と糖分を加え、容器の中で再度発酵させることで自然な炭酸を発生させる手法は、新しいものではなく、ベルギーを中心に世界中で採用されていた伝統的なビール造りの技法です。
ベルギーのセゾン・デュポンのようなクラシックなセゾンをはじめ、ベルギーの伝統的な醸造所ではごく一般的な手法として採用されてきた二次熟成製法は、自然の炭酸ガスが生成されるだけでなく、缶詰め機での充填が泡泡になって難しくなるほどの強い発泡を生み出すことも可能になります。セゾンの大きな特徴のひとつは、この力強い炭酸感(ケグでビールを注ぐ人を悩ませる原因でもありますが)であり、私たちのセゾンにもぜひ取り入れたいと考えました。
この製造方法には、時間と手間とコストがかかる反面、以下の2つの利点があります
■味わいの変化・深化を楽しめる
容器内二次発酵によりビール内に溶け込んだ酸素が消費され、極めて少なくなるため保存性が向上し、ビールがより長持ちします。また、同じ手法をとるシャンパンやワインのように、時間とともにビールが熟成され、味わいの変化・深化を生む効果も得られます。
■保存耐性の向上
二次発酵を行うことで、加熱殺菌(パスチャライゼーション)を行わずとも室温で安定して保存できる製品を作ることができるのです。保存耐性をつける一方で本来の味わいを損ねてしまう加熱殺菌については賛否ありますが、無濾過・非加熱にこだわってビール造りを行ってきた京都醸造にとって、この二次発酵製法はビールの持つ本来の魅力を損なうことなく、むしろより良い味わいに仕上げ、ベルギービールの伝統に忠実な本格的なビールに仕上げることができるという点で理想的な製造法だと考えています。
このような利点があるのであれば、採用しない手はないでしょう!しかし、この製法にも向き不向きがあり、ホッピーな現代的なビールのように味わいの劣化を進めてしまう要素が多いビールにはあまり向きません。例えば、ホップは酸素に対して非常に反応しやすく、これは酵母が酸素を消費する前の、二次発酵の初期段階に起こり得ます。私たちはこの点についてまだ十分な検証を行っていないため断定はできませんが、これまでのところ、容器内二次発酵を経たホッピーなビールで、人工的に炭酸を加えた新鮮なホッピービールと同じようなフレッシュさを維持できたものには出会っていません。 そうしたことから、セゾンを筆頭に昔から造られている古典的なスタイルは、二次発酵製法にとても向いていると考えられます。

今年の1月、私たちが大切にしてきた「一期一会」を思い切って二次発酵製法に切り替えたのち、自社のQAQC(品質管理)設備を活用し、味わいの変化だけでなくビール内で生じている変化をくまなく検査・観察を行ってきました。その結果、当初の狙い通りに溶存酸素量の低下と本来の味わいがしっかり維持されていることが確認できました。まさに発酵のなせる業です。さらに、しばらく保管した一期一会からは、かすかに味わいの変化・深化も感じられるようになり、二次発酵製法ならではの特性も確認できました。 一貫性・均一性を最重要視する大手メーカーには、味わいが変化する(してしまう)という代物は製品として扱いにくいと敬遠されるものだと思います。先にも述べた通り、コストも手間もかかるこの製法は効率や採算を追い求める現代にはあまりフィットしないかもしれません。しかし、フレッシュな味わいを何よりも重要視する私たちのようなクラフトビール醸造所だからこそできる大胆な試みであり、こうした実例が増えていくことによって、この古典的な製造方法が見直され、再び大きな脚光を浴びる日が来るかもしれません。実際、何年も寝かせたワインが得も言われぬ感動的な味わいを生むことを考えると、特別な機会に熟成させた一期一会で乾杯するのも悪くないですよね。
「要冷蔵」というのはクラフトビールの肝である“フレッシュな味わい”を維持するための条件となっていますが、国内の流通においては取り扱いやすさを損なう要因となり、導入への障壁になってきました。そのため取り扱いやすさを優先して加熱殺菌や濾過を施す事例もこの業界にはありますが、当社は時間と手間とコストをかけることで、フレッシュな味わいと取り扱いやすさの両方を兼ね備えたクラフトビールとして、より多くの人に身近な存在になることを選びました。

【二次発酵製法=発泡酒?】
二次発酵製法へと製法を変えると同時に、一期一会は「ビール」から「発泡酒」になりました。原材料は大きく変わっていませんが、なぜ発泡酒に変わったのでしょう。缶内二次発酵の際、タンクの中で一次発酵がほどほど完了した頃に、追加の酵母と一緒に酵母の栄養源となる糖分(主にグラニュー糖)を加えます。この糖分を酵母が消化する際に、炭酸、つまりきめ細やかな泡を発生させるのです。しかし同時に、この糖分を添加するタイミングによって、日本の酒税法では、ビールではなく発泡酒に分類されます。発泡酒と聞くと、ビールとは異なる印象を持たれる方もいらっしゃいますが、一期一会はビールと表記されている頃と大きく味わいが違うわけではなく、一期一会らしいバランスのよい味わいはそのままに、さらに二次発酵特有の美味しい泡、そして奥の深い酵母の熟成香を堪能できる設計です。
今回の変更により、扱いやすさと飲みごたえを両立したクラフトビールとして、さらに多くの方に「一期一会」を楽しんでいただけるようになったと自負しています。
冷暗所保管バージョンのラベルをまとった「一期一会」は、2025年10月から出回り始めます(中身はこれまでと変わりません)。ぜひ今後もご愛飲ください。