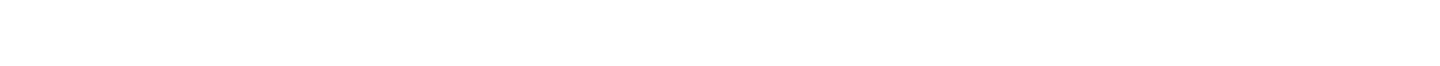祇園祭が宵山を迎え、京都がたくさんの人々でにぎわう頃、醸造チームの面々は、ある場所にホップの収穫に出かけました。訪れた先は、滋賀県・東近江市にあるFLORA FERMENTATION。

ご存知の方も多いかと思いますが、FLORAのブリュワーであり共同創業者であるKaiは、以前KBCでともに時間を過ごした仲間です。
そのFLORA FERMENTATIONの魅力のひとつは、ホップを自らの手で栽培していること。今年1月にKBC10周年記念のコラボのため彼らのブリュワリーを訪れた際に、自分たちで栽培したホップをぜひ試してみて欲しい!と、話してくれていました。
現在の日本では、ホップの商業的な栽培はあまり盛んではありません。しかし、必要な条件を満たし、手塩に掛けて栽培を行えば、その土地の個性を持ったとても良質なホップが出来ます。ホップの栽培には、適切な土地を選び、その土地の環境に合った種類のホップを選ぶことが重要なポイントになります。
通常ホップの収穫は、背高く伸びた蔓を収穫→専用の機械で毬花の部分を採る→乾燥させるという工程を経て、長期保管が可能なペレットに加工されます。そして、収穫を行う時期の特別なご褒美が、摘みたての新鮮な生のホップを使用したビールを造ること。
収穫後すぐに酸化をし始める生のホップにとって迅速な乾燥や加工はとても大切で、そうしないと、不快な安っぽいキャラクターが出てきてしまいます。つまりフレッシュな生ホップを使用したビールができるのは、ホップがたわわに実る時期に、収穫してからすぐに醸造に取り掛かかることが出来る条件が重なった時のみ、なのです。

さて、新鮮なホップの収穫というありがたいお誘いを受け、醸造チームの6人が車で滋賀に向かいました。FLORA FERMENTATIONには、先に書いたような大がかりな専用の機械はないので、手作業で毬花の採取を行います。ホップ畑で蔓を根本から切り、蔓と葉の間に隠れているホップの毬花までひとつずつ手で摘み取りました。まだ十分に大きくなっていないものや大きくなり過ぎたものは避け、自分たちの目で選定したホップは、最終的に13キロにもなりました。

今回、私たちが収穫したのは”チヌーク”という品種のホップ。驚いたのは、ホップ畑としてはまだまだ若い土壌で作られたにもかかわらずレベルの高いチヌークができていたこと。ホップはしっかりと根を張るまでに数年を要し、更にその間に雨や風などによって厳しい状況に置かれたり、流行病や虫害などの影響を受けてしまうと、毬花は使い物にならないところまで品質が劣化してしまうことがあります。そんな中、FLORAのホップ畑で収穫したチヌークは、アメリカ産のチヌークホップに似た豊かなアロマと、少しの樹脂感・柑橘感に加えて花や草のようなニュアンスも感じられ、とても良い印象を受けました。生のチヌークは水分を多く含んでいて、劣化を最小限に抑えるため、収穫後48時間以内に使用する(または乾燥させる)必要があることから、持ち帰ったホップは次の日の朝には仕込みを行いました。そしてその魅力を最大限に引き出すためにいくつかの工夫を行いました(これについては、また後日詳しく)。
このビールは、特別な材料を使用していること、コラボ醸造であることなどなど、様々な側面で楽しみなビールですが、特にいまは滋賀県・東近江市で作られたチヌークの個性がどのように出てくるかを楽しみにしています。このビールについての詳細はまた追ってお伝えしますが、日本ではあまり手に入らないあるいは一般的でなない、ユニークで特別な素材を紹介することに焦点を当てつつ、他ブリュワリーとコラボ醸造するビールシリーズ
4種のビールの第一弾となります。お見逃しなく。