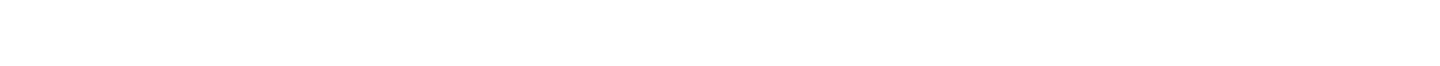型にはまらない自由な発想とコンセプトで、バラエティーに富んだスタイルや副原料を使用したビールを多数生み出してきたKBC2.0シリーズから、この度リリースするのは、あらゆる地域、時には地球の反対側から運ばれてきた原材料を合わせて造られることに着想を得て、遠く離れた土地の素材にフォーカスしたIPAシリーズ、「遙々(はるばる)」。
先に発売された「南の遥々(みなみのはるばる)」は、南の島から届いたハイビスカスの花を使用し、トロピカルホップと掛け合わせたホワイトIPA。そして第二弾となる「北の遥々(きたのはるばる)」では、北海道で自生するトウヒという植物の新芽を使用したIPAを造りました。

この「北の遥々」を造るために、あまり聞き慣れないトウヒの新芽を収穫するために北海道・雨竜(うりゅう)郡に採取しに行ったリードブルワーの歩(あゆむ)にインタビューしました。
-今回、トウヒの新芽を使用したIPAを造ることになったきっかけは?
歩:青森のBe Easy Brewingとのコラボ「ひばのきっぱず」を造った時に出たたくさんのアイデアのなかに松の新芽を使ったIPAがありました。残念ながらその時はシーズンが合わず、断念したのですが、ひょんなつながりで北海道で森林の研究をしている北川さんという方にその時の話をしたんです。そうしたら、北海道・雨竜郡にある研究林に松科のトウヒが自生しているよ、という話を聞かせてもらいました。トウヒというのは、松科トウヒ属のエゾマツの一種。すぐさまトウヒに興味があるという返事をすると、研究林を取り仕切っている方にも話を通してくださって、6月の新芽が出るころに現地で採取する機会を作ってくださいました。
-その雨竜研究林というのはどんな場所でしたか?
歩:旭川空港から2時間半ほど北に行ったところに名寄(なよろ)という街があり、私はそこに滞在することになりました。雨竜研究林は、そこからさらに車で30分ほど西に行ったところにあります。
この話が決まった当初は、5月にはトウヒの新芽の採取に行けるかな~という予想だったのですが、今年は5月にも降雪があったこともあり、新芽が出来るのが予想より遅く、6月中旬に訪問することになりました。
私が訪れた日は天気もよく、気温は27、8度程で、直射日光があるところではとても暑かったのですが、うっそうとした森林の中では日影も多く、木陰はとても気持ちのよいと感じる気候でした。

-トウヒの新芽を使ったビールというのは、北海道ではしばしば造られているものなのでしょうか?
歩:私もこれまで数度、目にしたことがありましたが、そんな頻繁に造られているわけではなさそうですね。もともとのアイデアは北欧や北米の日照期間が少なく、ホップが思うほど育たない地域で、ホップの代わりにビールに苦みや風味を付けるためにハーブなどの植物を使った”グルート”というビールから来ています。ヘッドブルワーのジェームズは、そのようなグルートをアラスカで飲んだことがあると話していました。
-では、研究林でトウヒの新芽を採取した当時の様子をもうすこし詳しく教えてくれますか。
歩:現地ではまず、北海道大学の小林真先生にリードいただき、演習林のメンテナンスの一環としてトウヒ、つまりエゾマツの伐採作業を行いました。その後、伐採したトウヒから新芽を採取しました。新芽は大きすぎると今回のビールには必要のないキャラクターが出てしまいますし、小さすぎると今度は採取が大変にもなります。ですので、3~5センチくらいのちょうどいい新芽をプチプチと地道に採取し、一日の終わりには13.5kgのトウヒを採取することができました。
伐採したての幹からは、針葉樹特有の爽やかで清々しい香りがして、伐採前よりもっと森の奥に入って、森林浴を堪能しているような気分になりました。新芽は、ハーバルな香りはもちろん、そこにベリーやシトラスといった果実っぽい香りを感じました。試しに口にふくんでみたのですが、白身魚のカルパッチョなんかに添えるのにいいな~と思いながら食べていましたよ。

-今回、ビールの材料を遙々北海道まで自らの手で収穫に行くという取り組みでしたが、滞在中の思い出はありますか?
歩:そうですね、現地では研究室のみなさんやそのご家族まで一緒に懇親会を開いてくださり、そこでは、近くのファームで作られた絶品ソーセージを振る舞ってもらいました。
さらに、初めてジンギスカン(羊肉)の煮込みも食べました。焼いたジンギスカンはこれまでも食べたことがあったのですが、甘辛いみそで味付けされていて、これも大変美味しかったですね!
-KBCの中では特に料理に造詣の深い歩さんらしく、食べ物の思い出が多いですね。では、歩さんが考えるこのトウヒの新芽IPA「北の遥々」にぴったりのお料理を教えてください。
歩:トウヒの新芽由来のベリーのような香りと樹脂感が効いた、ボディ感のあるクラシックなダブルIPAに仕上がっています。これに合わせるならば、ハーブをふんだんに使い、パリッと焼き上げた皮付きの豚肉”ポルケッタ”がおすすめです!油とハーブのコンビネーションがベリーや樹脂感と最高に合わさり、楽しめること間違いなしです。

-最後にトウヒの採取を通して、感じたことや印象的だったことを教えてください。
今回訪れた地域は、自然の豊かで、その自然が生み出す魅力的な植物や食べ物がたくさんありました。現地で採取したり、食べたりするので、普段京都で味わうよりフレッシュなものに触れることができ、貴重な経験になりました。現地でしか手に入れることの出来ない「豊かさ」が存在することを実感しました。
また、今回お世話になった北川さん、北海道大学の小林先生には、訪問前から本当に親切にしていただきました。現地でも、トウヒの新鮮さを保つならば枝ごとの持ち帰ることのがよいと教えてくださったり、研究内容についてもたくさんお話をしていただいたので、京都でビールを醸造しているだけでは知りえなかった知識や考えを得ることができました。
このビールを手に取って、このブログにたどり着いて、少しでも興味が湧いた方には、ぜひ僕が今回お世話になった小林先生の研究室HPも覗いてみて欲しいです!北海道の森林を舞台に多岐にわたる研究を進められています。
北海道大学 雨龍研究林 林長 小林 真先生 ”MAKOTO'S PLANT & SOIL LAB.”