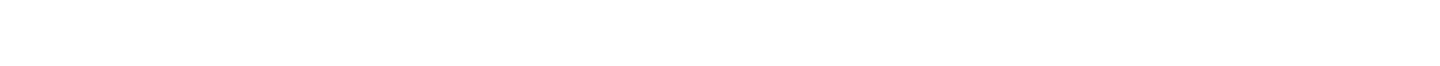2025年がはじまってすぐに新IPAシリーズ”Hop Idol”の第一弾である「コヒアネルソン」を発表しました。このシリーズでは、毎回モダンでインパクトのある一種類のホップにスポットライトを当てたIPAをリリースしていきます。昨年の六果撰シリーズでは、果物とホップのコンビネーションがテーマであった一方で、このHop IdolではIPAの醍醐味であるホップに再び回帰し、シングルホップにとことん深掘りするという少々大胆なコンセプトで一年取り組みます。乞うご期待。
では、今日紹介する2025年のもうひとつの新シリーズは、Hop Idolとは正反対に存在するようなビールにフォーカスしているといってもいいかもしれません。
新天地シリーズは、数年前に始まって以来、私たちにとって初めてのラガーシリーズとして展開してきました。しかし、2024年をもってこのシリーズに一旦終止符を打つという決断を下しました。それはなぜか?

「新天地」という名前が示すように、このシリーズは私たちにはとても大きな一歩でした。ラガービールへはその製造技術や文化に対するリスペクトを常に持ちながらも、創業初期には「絶対にラガーを作らない」と決めていました。しかし、あることがきっかけでその考えを改めな方向転換をすることになったのです。それは、結果的に私たちを「成長」させるきっかけになったとすら考えられるかもしれません。
かつての私たちにとって、クラフトビールは「インパクト」が全てでした。この価値観は、現代のクラフトビールシーンが生まれた背景から来ています。アメリカでは長い間、ビールと言えば、大手メーカーが造るシュワっと炭酸が強めで、特徴の少ない大量生産されたラガーを指していました。シンプルで、多くの人にとって「がぶ飲み」するための飲み物だったこのスタイルに対して、クラフトビールはその正反対を目指していたのです。つまり、個性的で、バラエティに富み、そしてインパクトのあるビールです。 そのことから、消費者にとってインパクトもなく、大手のビールとそこまで大きく変わらないと思われているラガーに、高い代金を支払うだけの価値があるのだろうか?と私たちは考えていました。

しかし、私たちが大きく変わり始めたのは、超ホッピーなIPAや、超ヘビーなインペリアルスタウトに味覚が少し疲れ始めたときでした。その頃になると、私たちは自然とラガーを手に取りたくなることが増えていました。しかし、同時に、それが画一的で大量生産されたものである必要はないと感じていて、無濾過、非加熱で丁寧に作られた本物のラガーの魅力に気づき始めたのです。
さらに、品質の高いラガーの職人的な側面にもますます惹き付けられ、感銘を受けるようになりました。IPAなど場合、ホップをさらに投入することで多少の不完全さをごまかすことができるかもしれませんが、ラガーのようにシンプルでクリーン、キレのあるスタイルでは、そうはいきません。このスタイルでは、繊細なホップのニュアンスとモルトのクラッカーのような滋味深い風味の絶妙なバランスが求められます。それだけに、隠しようがないのです。
そうしたことから、長らく意識しながらも近寄らなかったラガーに挑戦してみようと奮い立って始動したのが、新天地シリーズでした(厳密に言うと、かつてあった”解放”シリーズという醸造家がその時の気分や興味で好きなビールを造るという自由度の高いシリーズの中で、単発で造ったラガーに新天地と名付けたのが最初で、その後この挑戦を続けたいという意思の元でシリーズ化)。その中で、本場ドイツやチェコの古典的なピルスやへレス、デュンケルなどにも挑戦する一方で、強い発酵力を持つことで知られるKveik酵母を使ったラガーやお米を使ったライスラガーにも取り組んできました。
しかし、2025年を迎える今、この「新天地」という名前がすでに私たちにはしっくりこなくなっていると感じました。その理由はいくつかあります。
まず第一に、ラガーを作り始めて数年が経ち、いまでもラガーを「新境地」と呼べるのかのかという問いがあります。答えは恐らく、いいえです。最初は恐る恐る草を分けながら、にじるように進んだ経緯はありますが、今ではしっかりと過去に取り組んできた道を再び歩んでいるに過ぎず、私たちの実際の「フロンティア(境地)」はすでに新たな領域へとシフトしているのです。
また、消費者の視点から見ると、このシリーズがラガーの「二つの側面」をまたいでいることに気づきました。多くの人々が「ビール」が大手のビール以外にもたくさん存在するということを今では理解していますが、ラガーそのものも非常に多様であるという現実は、よほど詳しいビールファン以外にはあまり知られていないのが実情です。 クラフトビールファンは、スタウトやIPA、あるいは他のエールについてはよく知っているかもしれません。が、ラガーについてはとなると、きっと「炭酸強めのフツーのビールでしょ?」くらいにしか思っていないことがほとんどでしょう。
しかし、ラガーもまた、軽くてキレのあるものだけでなく、ボディがしっかりとした飲みごたえのあるラガーもあること。淡い色で喉を潤すのにぴったりなものだけでなく、ダークでモルティなラガーもあること。こうしたラガーの多様性は、まだあまり浸透していません。そして私たちの新天地シリーズは、人々がラガーとして理解しているスタンダードな面と、よりニッチなラガースタイルの両方をカバーしていました。
これはラガーの魅力を伝えたいという想いから幅広く展開しましたが、一方でこれが原因で、消費者が「このビールを買うかどうか」を瞬時に判断するのが難しい状況に陥っていました。たとえば、IPAシリーズなら、「ホッピーなビールが欲しい」というニーズを満たしてくれることが直感的に分かります。しかし、私たちが造っているラガーは、爽やかなものもあれば、じっくりと味わうモルティーなビールもあり、その違いが一目では伝わりにくかったのです。
私たちはヴィエナラガーやデュンケルを愛していましたが、実際に手に取って試した一部の人々にとって期待外れに感じられることもあると気づきました。どんなに良いビールであっても、それが飲む人の気分や期待に合わなければ、思う存分楽しむことが難しくなってしまうのです。
そこで私たちは、考えました。このシリーズをより明確に分けるのはどうか、と。今年の前半は、これまで以上に印象的なラガーを自由に作れるようにしたいと考えていたので、コラボレーションシリーズの「仲間」や「KBC 2.0」のもとで、そうしたビールを展開していきます。その一方で、親しみやすさや純粋な美味しさを約束するような「本当に素晴らしいラガー」もひきつづき造っていきたいと思っています。
そこで紹介するのが、「巡り巡って(英名:Round and Round)」シリーズです。このシリーズは、一言でいうとライトなラガーの持つ「日常性の尊さ」を称えるものです。ライトラガーというカテゴリーの中でも、私たちが惹かれる微妙なニュアンスや多様性が実際にはたくさん存在します。そして、こうした一見飾り気の少ないライトラガーですが、実直な魅力が多く詰まっていることから、次のような誰にでもありそうな「日常的な瞬間」を美味しく支えるような存在だと感じました。
- 仕事終わりの最初の一杯
- 忙しい一日を終えて、家に帰ったときにまず楽しみたいビール(仕事に追われたハードな日でも、活動的に楽しんだ休みの日でも)
- 夕食を始めるときに飲みたいけど、喉も乾いているときに選ぶビール
- (大小問わず)勝利を祝うときに乾杯するビール
私たちは、毎日がハレではなく、ケの連続のような日常の中で生活しています。しかし、連綿とつづく日常に退屈するでもなく、続けていられるのには、その日常を潤す小さな「好き」が生活のなかに点在しているからでしょう。この「巡り巡って」のラガービールも日常の中にすっと寄り添う最高のビールとして、驚くほどに親しみやすい、そしてしっかり美味しいスタイルを選んだものです。
軽めで爽快な味わいなもの、それから少し苦味が効いていてキリっといきたい時にぴったりなもの、そしてほのかにボディ感を持たせて余韻を楽しめるもの、など。それぞれが世界で最も愛されるビールタイプで、その飾らない特徴から日常における瞬間瞬間に溶けこむように自然で、それでいてしっかり最適な形でフィットするように考えました。そして、その毎日をぱっと彩るには、無濾過非殺菌で、材料・製法にも一切妥協のない、本格的ラガーで、というのが私たちからの提案なのです。

年4回のリリースを予定していて、その第一弾は、ジャーマンピルス「いただきます」。伝統的な製造に使われる材料を意識しながらも、ほんの少しモダンなホップによる味わいの仕掛けが隠されていたりと、お気に入りにしてもらえること間違いなしの一杯です。そして、それぞれの名前には、日々の生活の中で交わされる言葉を使うことにしました。
私たちは以前、「その夜に飲む唯一のビールになる必要はない」と言っていました。クラフトビールの多様性が大好きで、他のブルワリーが造るビールが私たちのものと対照的であることも楽しんでいます。しかし、こうも思っています。私たちの名前がメニューに載っているのを見たときに、まず最初に手に取ってもらえるビールでありたい。そして、その夜の後半にまた戻ってきたくなるビールでもありたい、と。まさに、このシリーズこそが、あなたの“最初の一杯”にふさわしいビールかもしれません。、そしてもしかしたら“二杯目”にも選ばれるビールを目指しています。