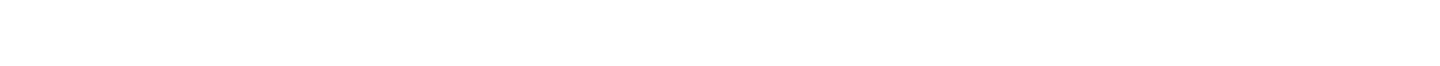京都醸造10周年記念イベント「なみなみと」まで、いよいよ1週間を切りました。社内は5/10に向けての準備に奔走していて、いつにも増して慌ただしい雰囲気で満ちています。当日来場される皆さんはもちろん、ゲストブルワリーの面々、そしてボランティアで参加してくれるメンバーにも楽しんでもらえるイベントになるよう願っています!
さて、本日は、西東京は立川にあるSakamichi Brewing(以下SMB)とのコラボについてご紹介したいと思います。

SMBが創業したのは、2020年3月のこと。前回のBlack Tide Brewingと同様にコロナ禍の影響が大きい時期にビール造りを始めることになりました。創業からわずか1ヶ月後に、感染症が全国で急拡大したことから、いち早く飲食店の酒類の提供に関する制限が東京都でも設けられ、動き始めた矢先だった彼らも一時的に営業を停止せざるを得なくなってしまいました。
しかし不幸中の幸いだったのは、当時のSMBは共同創業者のマシューとダニエルの2人だけで運営していたため、大きな出費にすぐ頭を抱えることはなかったということ。とはいえ、当初立てていた計画を見直す必要があると、彼らはすぐに意識を変え、歩み出します。

もともとの構想では、ブルワリーとタップルームを同時に立ち上げる予定でした。ところが、ビールの製造免許を取得するには設備購入などに使う資金が必要で、その資金を得るには製造免許が必要、というジレンマに直面します。そこで2人はまずタップルームを先にオープンし、他の小規模なブルワリーで委託醸造を行うという道を選びました。そして、そこで造らせてもらった自分たちのビールと、委託製造に協力してくれたブルワリーのビールをゲストビールとしてタップルームで提供し、その売上を自分たちの設備購入資金に充てるという新たな構想を築きました。

これについてもう少し踏み込むとすれば、マシューがSMBを立ち上げる前に、醸造家としての経験を積んでいた時の話に遡ります。その頃、ベアードで長年ヘッドブルワーを務めていたクリスプール氏が独立し、自身のブルワリーである潮風ブルーラボを千葉で立ち上げることになりました。その潮風はスムーズに事業を軌道に乗せるため委託醸造のモデルを採用しており、そうした縁でマシューは多くのブルワリーとのネットワークを築くことができたのです。そして、それが結果として、構想の練り直しを迫られたSMBを絶望の淵に立たせることなく、新たなモデルに導くことになったのです。
さて、醸造所よりタップルームを先にオープンさせたSMBですが、その後もコロナの波が寄せては返すをくりかえす度に、営業を再開しては再び休業するということになり、収益は安定しませんでした。その影響で、醸造設備導入の実現も次第に遠のいていきました。 しかし、こんな中でも転機が訪れます。SMBがながらく相談を持ち掛けていた地元の銀行が、当時の飲食やビール業界が面している苦境を知り、そんな逆境の中でも少しずつでも着実に成長していたSMBに感心し、手を差し伸べてくれることとなったのです。
2022年、ついにSMBは融資を受け、500リットル規模の醸造設備を購入、同年の12月には、初めて自社設備でのビール醸造を実現しました。創業から2年半以上を要したものの、その間に彼らが築きあげてきたものは大きく、そこには自身の設備で造るビールを待ち望む地元の多くのファンがいました。
SMBのタップルームのある立川駅は、東京駅から約45分というアクセスの良さから、西東京における最大の駅のひとつであり、特にラッシュ時の利用客の数は圧巻です。そんな立川駅から徒歩5分という立地にあるSMBのタップルームは、そのエリアでクラフトビールを提供する数少ない店のひとつです。昨年11月には事業を拡大し、駅の北側にも新たなタップルームをオープンさせました。そして今年2月、地域への貢献が評価され、立川市から「輝く個店」賞を贈られることになったのです。(参照リンク)。

ビールの醸造に2つのタップルームの運営にと、忙しい日々を送っているSMBの2人ですが、Black Tideと同様に、この2年間のホップセレクションのためのニュージーランド訪問を通じて、私たちは親交を深め、ついに今回のコラボが実現することになりました。
では、どんなビールを一緒につくろうかと話をする中で、マシューとダニエルが最初に出会ったきっかけが、自転車でのツーリングだったということにちなんでテーマを「自転車」にし、自転車乗りが好むビールとして知られる「ラドラー」がぴったりではないかという話になりました(Sakamichiの名前も山の中のアップダウンを駆け抜けるツーリングから取ったそう)。そしてすこし無理がありますが、京都醸造側でも、自転車は非常に重要なもので、京都の比較的平坦な地形の影響もあり、社員の9割ほどが自転車通勤をしているという共通点もありました。

ラドラーは20世紀初頭のドイツで誕生しました。 ミュンヘン郊外のディーゼンホーフェン地方でバーを営んでいたフランツ・クーグラーという人物が、自身の手によって開通させたミュンヘンから自分の酒場までのサイクリングトレイルが功を奏して、ある晴れた日には13,000人ものサイクリストでごった返す事態になりました。フランツ氏の大喜びは束の間、店で準備していたビール(ピルスナー)が底をつきそうになった時、彼がとっさに店にあったレモンソーダとビールを混ぜて提供し、訪れる全員にビールを行き渡らせようとしたのです。付け焼刃的なこの判断が、またうまくいき、このビールのレモンソーダ割が大好評となり、以後「ラドラー(ドイツ語で“サイクリスト”の意)」と呼ばれるようになったとのこと。
このラドラーのストーリーを受けて、マシューはツール・ド・フランスを象徴する“赤と黄色”のラドラーを作ってはどうかと提案してくれました。 ツール・ド・フランスは世界最古で最も権威ある自転車レースで、レース期間中それぞれのステージで順位を取り合います。その日のステージで首位に立っている選手には、「マイヨ・ジョーヌ」という"黄色い"ジャージが着せられ、一方で最下位になった選手には「ランタン・ルージュ(赤い提灯)」という称号が与えられます。
このコラボでは、SMBが"黄色"、京都醸造が“赤”をビールで表現すると決め、私たちは「ルビーレッドグレープフルーツ」を使ったラドラーを造ることにしました。 このルビーレッドというのは、グレープフルーツの中でも栽培が難しいそうだが、非常に甘みがしっかりあり、酸味や苦味が控えめなのが特徴。そして自然な甘みとしてモンクフルーツ(羅漢果、らかんか)を加え、ルビーレッドのほのかな酸味と柑橘感を上手く調和させることで、やわらかくクリーンな"ラドラー"になるように仕上げました。そして最下位にも与えられる称号というので、「ビリの誉れ」と名付けました。

一方、SMB側は、レモンの酸味と爽やかな香りを楽しめる"瀬戸内レモン"を使ったラドラー、「Maillot Jaune(マイヨ・ジョーヌ)」が出来たそうです。 通常、SMBのビールはそのほとんどがタップルームで使われることが多いそうなのですが、この"瀬戸内レモン"ラドラーは5/10の私たちの周年イベント「なみなみと」でも提供してくれるそうなので、こちらで造った「ビリの誉れ」と一緒に楽しんでもらえます。お楽しみに!!